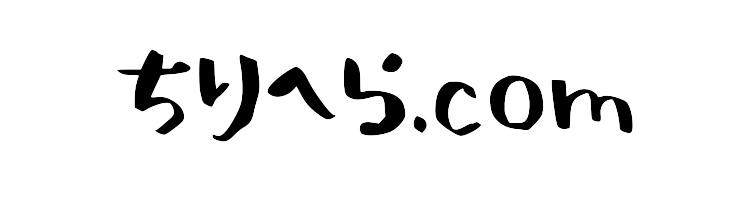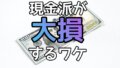「インフレって最近よく聞くけど一体なんなのかよくわからない…」という方も多いかと思います。
こういった金融の専門用語って調べてもむずかしいことばかり書いてあってわかりにくいんですよね。
そこで今回はこのインフレに関してめちゃくちゃ噛み砕いてわかりやすくまとめました。
前半部分だけ読んでいただければインフレについて充分理解することができますからインフレがなにか知りたいという方は前半だけでOKです。
後半部分ではインフレをもっと掘り下げて解説しています。
インフレとは?
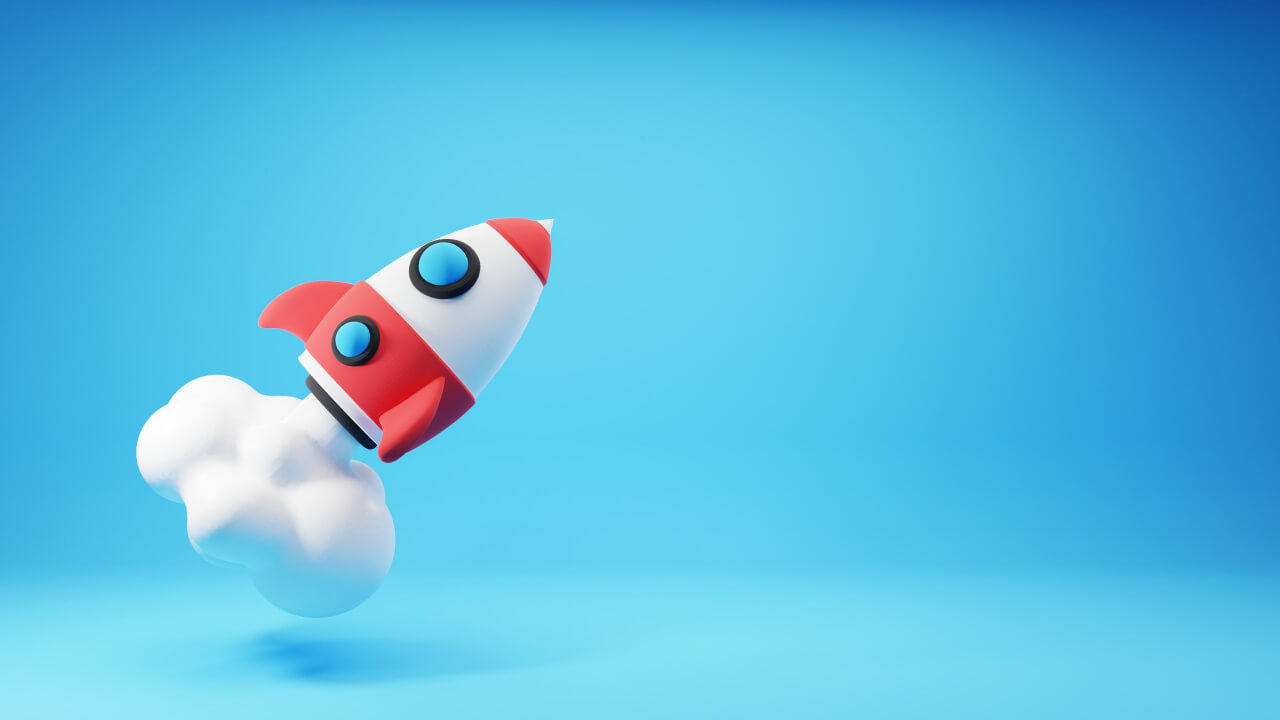
インフレとはインフレーションの略称でモノやサービスの値段が継続的に上昇することです。
つまりインフレを一言であらわすと「物価上昇」となります。
モノの値段が上がっているわけですから「お金の価値が下がっている」とも言えますよね。
インフレに関してシンプルにまとめると上記のようになります。
ではもうすこし噛み砕いてわかりやすくインフレを考えてみましょう。
またインフレだけではなくお金のことについてこれから学びたいという方はこちらの書籍がとても読みやすくておすすめですよ。
物価の上昇とお金の価値
インフレを起こすと「モノやサービスの値段が継続的に上がります」
これは言い換えると「お金の価値が継続的に下がる」と考えられます。

1万円は1万円のままなんだから価値は変わらないでしょ
これは大きな間違いでインフレ(物価上昇)するとお金の価値は下がってしまいます。
わかりやすくだいぶ極端な例えで考えてみましょう。
現在一杯100円で買えるコーヒーが来年には一杯400円と4倍に値上がりしたとします。
このときにコーヒーの量や品質が変わっていなければ純粋にコーヒーを買うのにたくさんのお金が必要になったということですよね。
つまり一杯のコーヒーに対してお金の価値が4分の1になってしまったと考えることができます。
インフレではコーヒーだけではなく食料品や生活インフラ、サービスの価格も上昇します。
そのためインフレが進むと今まで通りの生活を送るためには今よりもたくさんのお金が必要になります。
もし現在年間200万円の支出で生活をしている方は今と同じ生活をするのに年間800万円必要になるということです。
これはずいぶん極端なたとえでしたが物価上昇(インフレ)した分お金の価値が減少してしまうのがポイントです。
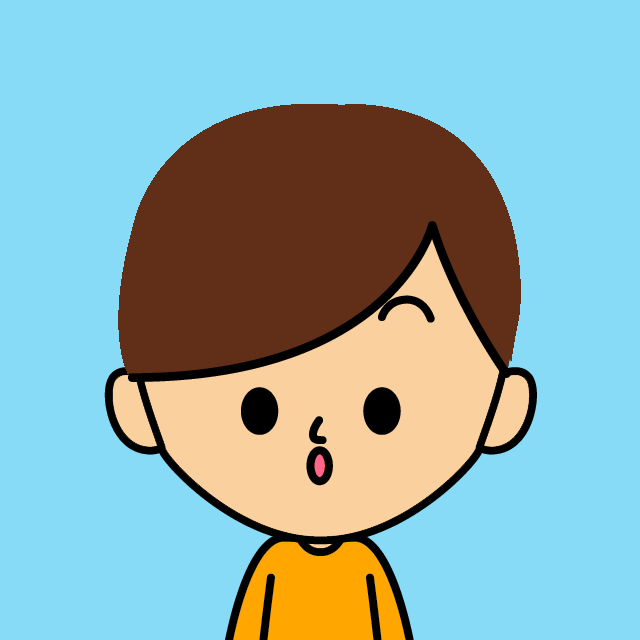
1万円という額面は変わらなくても1万円で買えるものが減ってしまうということですね。
・インフレとは物価が上昇すること
・お金の価値は物価によって増減する
なんでインフレするの?

インフレとはモノやサービスの値段が継続的に上がることですがなにもなく突然物価が上昇しているわけではないんですね。
まずモノの値段は需要と供給のバランスで決まります。
欲しい人(需要)がたくさんいるのに商品(供給)が足りないと物価はゆるやかに上昇(インフレ)していきます。
逆に商品(供給)がたくさんあるのに欲しい人(需要)が少ないと物価は下落(デフレ)していきます。
ですが欲しい人がたくさんいても、みんながお金を持っていなければ商品を買うことができませんよね。
そのためインフレでとても重要なのが世の中に出回るお金の供給量なんですね。
世の中に出回るお金の量が増えれば消費が活発になり物価は上昇、景気も良くなります。
逆に世の中に出回るお金の量が減ると消費が冷え込み物価は下落、景気は悪くなってしまいます。
このようにお金の供給量が経済にあたえる影響はとても大きいため政府が世の中に出回るお金の量を適切に調節することで経済の成長をサポートしているんですね。
良いインフレと悪いインフレ
インフレには「良いインフレ」と「悪いインフレ」があります。

インフレすると負担が増えるから良いことなんてないんじゃない…?
と思いますよね。
ですが経済の健全な成長にはゆるやかなインフレが最適とされており、日本も年間2%のインフレを目標としています。
ここでは良いインフレと悪いインフレの違いをまとめました。
良いインフレ
良いインフレとは需要が供給を上回ったときに発生するインフレです。
良いインフレが起こると経済はゆるやかに成長していくことができます。
ではこの良いインフレが経済にあたえる影響を見てみましょう。
1.需要(欲しい人)が供給(商品数)を上回る
2.商品の価格が上昇する
3.商品を提供している企業の売上げが増える
4.企業で働く従業員の賃金が増える
5.給与が増えると購買意欲が上がり消費活動が活発になる
6.1に戻る
上記のように物価が上昇しても賃金が連鎖して上昇することで消費活動は活発になり、景気が良くなります。
悪いインフレ
悪いインフレとは原材料費や人件費などの生産コストが値上がりすることで発生するインフレです。
生産コストが上がることで企業が販売価格を維持することがむずかしくなり価格を引き上げることで起こります。
前述した良いインフレとの大きな違いは価格は上昇しても企業の利益は変わらないという点なんですね。
企業の利益が変わりませんから従業員の賃金も増えません。
つまり物価の上昇と賃金の上昇が連鎖しないということですね。
賃金が上昇しないのに物価が上昇してしまうと買い控えがおきて消費が冷え込んでしまいます。
そうなるとさらに企業の利益が減り、従業員の賃金が減少し…という悪循環が生まれて景気が悪くなってしまうんですね。
このような生産コストが上昇することで発生するインフレを「コストプッシュインフレ」と言います。
物価と為替の関係
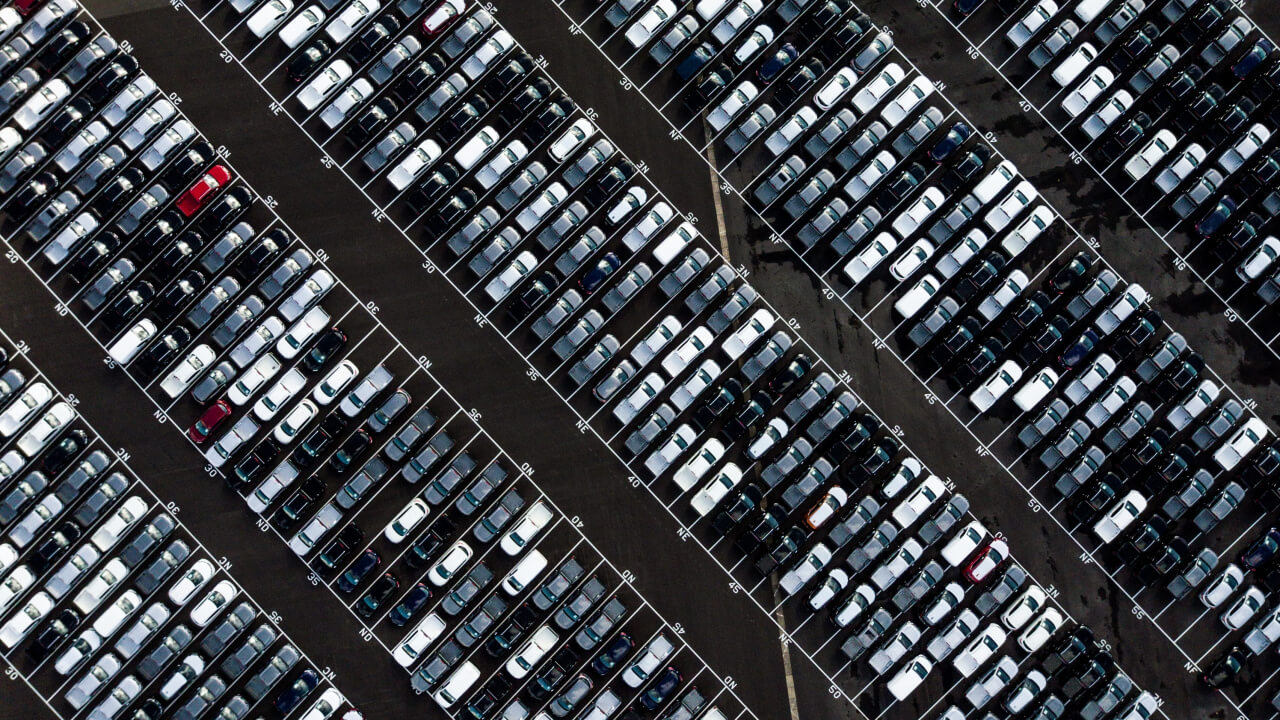
為替には海外の商品の価格と国内の商品の価格の差を吸収する役割があるんですね。
基本的にインフレしている国の通貨は安くなりデフレしている国の通貨は高くなります。
ちょっとわかりづらいので日本とアメリカの車の価格で考えてみましょう。
・為替は1ドル=100円
・日本の車の価格は100万円
・アメリカの車の価格は1万ドル(100万円)
上記の条件で日本がインフレしていてアメリカの物価は変わらないとします。
日本はインフレしていますので車の価格が上昇し日本で販売されている車は1台120万円になったとします。
ですがアメリカの物価は変わりませんのでアメリカで販売されている車は1台1万ドル(100万円)のままです。
そのため日本で車を買わずに円をドルに替えてアメリカで車を購入するだけで20万円も安く車が買えてしまうということなんですね。
またアメリカと日本の物価の差は車だけではなく食品や家電、穀物などさまざまな商品で価格の差が発生します。
つまりアメリカのモノが円で買いやすくなるということです。
そうなると円をドルに替えてアメリカのモノを購入する人が増えます。
またアメリカで買った商品を日本で転売する業者もたくさん現れるでしょう。
この場合なにが起こるかというと円が大量に売られて大量のドルが買われることでドルの需要が高まり、円安ドル高となります。
こうなるともともと1ドル=100円だった為替も1ドル=100円→110円→120円と徐々に円安が進みます。
円安が進むことで日本の車の価格120万円、アメリカの車の価格1万ドル(120万円)となり物価の差は為替によって埋められるんですね。
このように物価は世界の経済とも密接に繋がっています。
まとめ
今回は物価が上昇するインフレに関してまとめました。
物価の上昇や下落、為替との関係など少し複雑でわかりにくいですよね。
でも基本はとてもシンプルで需要が多ければ高くなりますし、需要が少なければ安くなります。
これは物価だけでなく為替や株などにも当てはまります。
そのため経済でわかりにくいことがあった場合は需要と供給がどうなっているか?を考えるのがベストですよ。
お金の基本を学びたい方にはこちらがおすすめです。